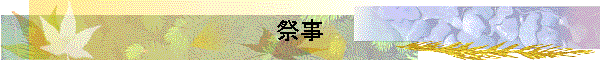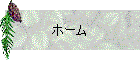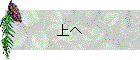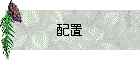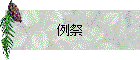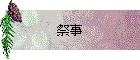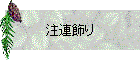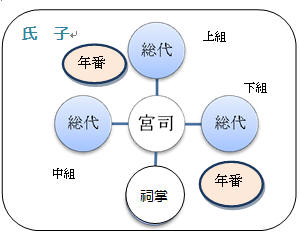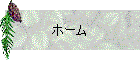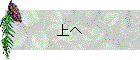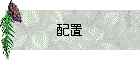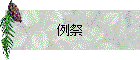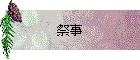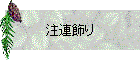|
|
行事名
(目的・内容) |
氏子の役割・参加 |
我が家の役割(祠掌) |
|
1月 |
年初め
|
初詣
年番 ~ 幟立て
|
�正月3が日は朝夕に燈明を点ける
�神社に朝は雑煮・夜はご飯を供える
(10か所)
�元旦朝は、お神酒・鏡餅を供える
|
|
2月 |
祈年祭(きねんさい)
(今年の五穀の豊穣祈願・生業の発展・国家と国民の安泰を祈る祭り)
常会(役員改選等)
|
宮司・総代参加

氏子全員出席
|
�供物(6品)の用意〜神饌台に並べる
�玉串の準備
�直会(なおらい)の準備
|
|
3月 |
例祭
(れいさい)
(一年に一度のお祭り〜3大祭祀の一つ)
|
氏子全員出席・祝詞、直会
*準備 (清掃・供物の袋づめ・幟だて)
年番〜赤飯の奉納・直会の準備
|
�氏子の数と奉納者のお神札作成
�玉串(榊)・神饌物用意
〜祈年祭に準ずる
宮司が持参した幣帛料を奉納する。

|
|
4月 |
禦(ふせぎ)
(邪悪なものの侵入を防ぐ)
|
氏子全員出席
年番〜四方固め
 |
�神札--
氏子の人数分
�四方固めの神札4枚〜用意
�玉串(榊)供物用意
〜(祈年祭に準じる)
�御酒壷にいれる酒1升を用意する
|
|
6月 |
大祓い
|
年番から氏子に配付
|
宮司が氏子分の大祓いを作りに来る
|
|
7月8月 |
1日の禦(ふせぎ)
灯篭初めの行事
地蔵さまの供養
|
~1990年前後に廃止となる。
|
|
11月 |
新嘗祭 (にいなめさい)
新穀感謝祭
(新穀を捧げて神様に感謝の意を表わすお祭り)
|
宮司・氏子総代3名・祠掌出席
総代〜宮司からのお札(天照大神)を
氏子に配付
|
�供物(6品)の用意〜神饌台に並べる
�玉串の準備
�直会(なおらい)の準備
|
|
12 月 |
注
連
飾
り(しめかざり)
(鳥居・神木などの注連を新年に備え新しくする〜藁で編む)
|
氏子全員出席
年番〜12月下旬に各家庭から徴収した年俸を宮司へ持参
・大祓いを氏子に配付
|
≪事前準備≫
宮司〜「紙垂・大祓い・御幣(幣束ヘイソク)」作成
≪当日≫
�「杵」を2本用意
〜藁をたたいて柔らかくする
�お茶・茶菓子の用意
�大祓いを年番に渡す
12月31日⇒
初詣のため、拝殿を開ける
|
|
毎月 |
神社掃除 |
氏子3人ずつ交代で実施
夏期:全員で実施 |
拝殿を開ける
お茶・お茶菓子の用意の用意 |
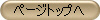 |