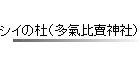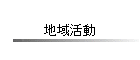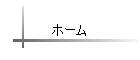
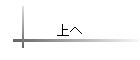
2 年中行事やこの地域に残っている習俗
この地域の習俗として残っているものを列挙し、特に独特の珍しいものは下線で示します.
(1)年中行事
� カマジメ
正月を迎えるために家の神々のお札や注連飾りを取り換えることをいう。一夜飾りは避けて30日に交換する。古いお札は神社でお焚きあげをしてもらうか、個別焼却する。
� 恵比寿講
恵比寿様は商売繁盛だけではなく、この地域では田やかまどの神としても古くから信仰されていた。1月20日に座敷に台を作って恵比寿様と大黒様を祀ってご飯やけんちん汁などを供えたという。
� 節分
炒り豆を一升枡にいれ豆まきを行う。焼いた鰯を家の入口に刺し魔よけにする。
� 初午(稲荷様の祭日)
2月の最初の午の日に炒った大豆とおろした大根を醤油で煮て神さまに供える。
「スミツカレ(リ)」を作る
  |
� 七夕
8月の七夕の前日には竹飾りや、マコモの馬を作った。川や沼で刈ったマコモを乾かして馬を2頭作り、竹飾りを中心に向かい合わせて飾った。(ここ十数年は、マコモも採取出来ず行われていない)
� お盆(迎え盆・送り盆)
盆棚をつくり、13日に先祖さまを提灯を下げてお迎えに行く。墓地では、ろうそくに火を点け、先祖さまの墓石の前を「お迎えに来ました。どうぞお入りください」と一周し、提灯の灯が消えぬように家に導き、縁側から上がり盆棚に迎え火を移す。
15日の夜又は16日の朝に、先祖様をお墓にお送りする。
*七草・彼岸・十五夜・冬至などの行事の習俗は他の地域とあまり変わらない。
(2)出産・成長と儀礼
昔は、成人以前に様々な病気で亡くなることが多かったため、子どもが育つ節目節目に人々が集まって無事な成長を祝うという行事が、地域にも残っている。
� 子授け祈願・安産祈願
「子どもが授かるように」「無事に産まれますように」と多気比売神社に参拝する人が多くいた。無事な出産後は、お礼の参拝に来る人も多い。
� お七夜
産後7日目のお祝いや名づけを行う。決まった名前は、「命名○○」と書いて神棚の下に貼る。
� 宮参り
男の子は21日、女の子は31日目(最近は、この前後の良い日を選んでいる)に神社を参拝し無事な成長に感謝する。親元から贈られた晴れ着をかけて姑が赤ん坊を抱いてお参りする。
� 初山
産まれて初めて7月1日を迎える子どもの額に神印を押してもらい、無事な成長を祈願する。
*お食い初め、初誕生、七五三などの成長を祝う風習は他の地域と同様である。
All right reserved by kinta Ⓡ2011